
2011年の日本初演以来、上演の度に若手俳優たちの火花散る演技が話題の『スリル・ミー』。スティーヴン・ドルギノフ(脚本・作詞作曲)が実際に起こった事件をもとに描いたこのミュージカルの最新版で、新たな“私”役を演じているのが松岡広大さんです。
オーディションで勝ち取ったというこの役をどうとらえ、構築してきたのか。開幕間近のある日、たっぷりとうかがいました。
【あらすじ】監獄で審理される、ある囚人の仮出獄。54歳のこの囚人は、審理官に事件の本当の動機、隠された真実を語るよう求められ、静かに当時を振り返る。19歳の“私”は幼馴染の“彼”と久々に再会。ある“契約”を交わした二人は、放火や窃盗を重ねるが、”超人”を自認する“彼”はそれに飽き足らず、“偉大なる犯罪”を提案する…。

技巧に走らず、若さを
生かして体当たりするしか
ない、と思っています
――松岡さんは『NARUTO」『るろうに剣心』「Inspire陰陽師』などでキレのある動きを見せていらっしゃいましたが、本作にはそういったアクションがありません。敢えてそういう作品を選ばれたのでしょうか?
「そうですね。動きだけが表現じゃないし、動けるということだけを自負してやってきたわけではありません。動けるからそういった作品に起用していただいたのかもしれませんが、今の僕は、言葉の表現に興味があって、これまでとは違う作品もやってみたいと思いました」
――何か、きっかけになる作品があって、言葉の面白さに目覚めてのことだったのでしょうか?
「僕は10代の頃に今回、ご一緒している栗山民也さんの演出作品を観ていたし、20歳の時に劇団新感線の舞台に出演して、いのうえひでのりさんの演出を受けたり、『恐るべき子供たち』で白井晃さんに出会ったことも大きかったです。それと、10代の頃2.5次元の舞台が続いたことで、20代は2.5次元作品以外も出来る俳優になりたい、とも思ったんです」
――今回の出演はオーディションで勝ち取られたとうかがいましたが、オーディションではどういう部分を求められていると感じましたか?
「どれだけ言語を丁寧に扱えるか、試されているような気がしました。歌もそうだけど、どれだけ言葉を自分のものにできるか。ただ読める、ただ歌えるだけではなく、どれだけ自分のものに近づけられるかが問われたのかな、と」
――それはご自身で準備したものをご覧いただく形ですか、それともその場で「こういう風にやってみてください」と指示があるとか?
「自分の持ってきたものを披露するだけで、チャンスは一回きりです。オーディションではだいたいそうですね。後から何か言ったりはできないです」
――では、解釈が違っていたらその時点で終わってしまう…。
「お芝居は正解があるものではないので、その人がどう感じたかを見ているんだと思います。自分が信じたものをどれだけ表現できるか、というところに重きが置かれているのではないかなと。」
――この作品の面白さを、どうとらえていますか?
「実際に起きた事件がもとになっているのですが、それなら新聞記事を読めばいい、と思う人もいらっしゃるかもしれません。でも、人間が普段は見たくなかったり、目を伏せてしまうようなものをつまびらかにするのが演劇の強みであったり、面白いところだと思います」
――本作で言えば、人間のどす黒い感情であったり?
「善悪であったり。それはこの社会に生きている僕たちへの教訓であって、それを再確認する場なのかもしれません。僕らの生活圏にもこういう問題は入ってきてるよということを確認できるような作品ですね」
――ロマンティックな愛の物語ではないわけですね。
「そういう側面だけで話せるものではないし、一つの柱だけじゃ成り立っていないような気がします。僕らは作品のテーマを一つに絞りがちだけど、この作品に関しては、“究極の愛”に絞ったり、美化したりしてしまうのは少し違うというか、そうなってしまわないようにと思っています。観る人によって違うとらえ方ができるようになっているし、余白があって説明しすぎていないのが、この作品の大好きなところです」
――本作には「私」「彼」の二人の人物が登場しますが、はじめに台本を読んだとき、直観的にどちらをやってみたいと思われましたか?
「“私”です、迷わず。54歳と19歳を、照明一つで瞬時に演じ分けることができる。今、23歳の僕が54歳と19歳を演じたら、どんなことを伝えられるんだろう、自分はどう感じるだろう、と思いました。誰かに追随しがちな人物、というのも面白いなと思いました」
――追随しがちな「私」の内面がどう動いてゆくか、は本作のポイントの一つですね。
「リチャード(彼)は(悪事を重ねるにつれ)だんだん物足りなくなり、殺人を計画しますが、“私”自身も、殺人は悪だとわかっていながらも、彼についていこうとします。彼を求めるあまりの殺人であって、それが理由でなければ悪を正当化できなかったのかなと思います。なので、あの重要な落し物が故意だったのか偶然だったのかと言えば、僕の中で有力なのは、後者かな。もともとは思いもよらなかったのではないかなと思うんです」
――観客としては、そのあたりの心の動きを想像しながら見るのも、本作の醍醐味です。
「僕自身は説明しすぎないようにと思っていますし、どこに片鱗があるのか、ということも読み解かせたくないです(笑)。わかりやすいものにはしたくないですね」
――栗山さんのお稽古はいかがですか?
「台詞一行一行にご指摘をいただいて、台本は真っ黒になっています(笑)。でも稽古が進む中で、ノートの質が変わったというか、(終盤の今は)心理的なものだったり、俳優としての基礎的なものを教えていただいていると感じます」
――どんなところで栗山さんに信頼を感じますか?
「とにかく、早くダメ出しをもらいたいという気持ちにさせてくれるほど、安心感があります。栗山さんは“これはこうだ”と明言するわけではなく、どこかで考えさせる余地を作って下さって、その余地は僕らが考えなればいけないんです。人間の想像力を信じている。出来ないことは言わない方だと思うので、その点で愛情を感じますし、そこに甘えることなく、自分のできることを提示していきたいと思っています」
――3組それぞれにカラーがあるかと思いますが、松岡・山崎組のカラーは?
「今回、3組で渡されている柱が違うんです。僕らは“生の暴走、若さの暴走”、田代さん・新納さん組は”究極の愛”、そして成河さん・福士さん組は”資本主義の病”、という柱でやっています。資本主義社会には格差が生まれて、優れたもの、創造できるものが生き残ることができ、それ以外は死ぬわけで、他人より秀でていないとこの競争社会では生き残れないという枠組みがある中で、若い僕らとしては、危険に対する興味だったり、後から気づいて後悔したりといった感情を全身で表現していけたらと思っています」
――「超人」という言葉には完璧なエリートというようなイメージがありますが、松岡組ではもっと“青い”存在、ということでしょうか。
「そういう部分もありますね。ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』も読みましたが、そこでは、これまでの社会、新旧の壁を壊して、自分たちで善悪を判断して生きていくという意味で“超人”という言葉が出てきていて、本作で“彼”が言っているような、全知全能の比類なき人間になれと言っているわけではないんです。でも、行き詰った人たちは(誤解して)連れていかれてしまうんでしょうね。“彼”もまた、思想をかみ砕けていない状態で暴走してしまったのかなと思います」
――今回、ご自身の中でテーマにされていることはありますか?
「想像力を働かせて、技巧に走らないようにする、ということを心がけています」
――テクニックを使ったほうが楽である、と?
「よく“こうすると演劇的”というようなことを言いますが、そういうテクニックはこの二人芝居では必要ないんじゃないかと思っています。19歳の時の彼らに僕らは近い年齢なので、それを生かして、体当たりでやるしかないと思っています」
――どんな舞台になりそうでしょうか?
「若さとは言っても、決して勢いだけでは終わらないと思います。作品のどこかで、善悪についてどう思うか、昔と今を比べて何が今、近づいてきているか、性別に関係なく、何か感じていただけたらいいなと思っています」
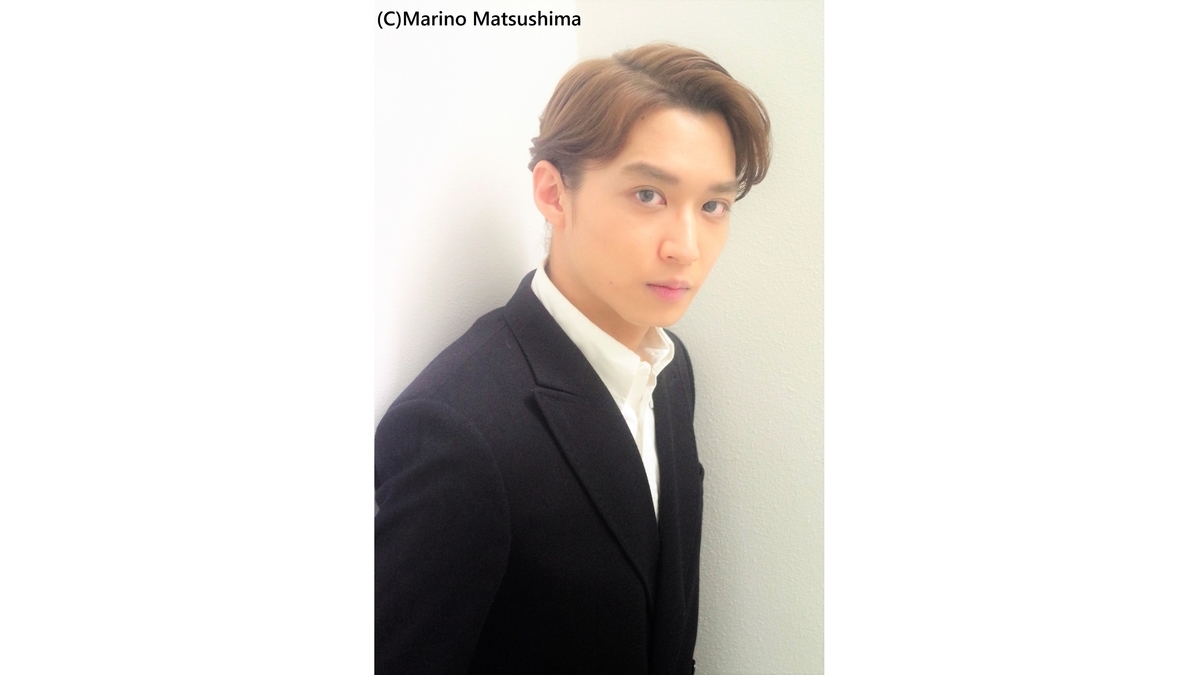
――プロフィールについても少しうかがわせてください。松岡さんの所属事務所では、先輩の俳優さんからじっくり、演技について講義というか、お話をうかがうシステムがあるとうかがったことがあります。松岡さんもそういった経験はありますか?
「僕の場合は、(システムに関係なく)橋本淳さんにたくさん教えていただきました。橋本さんは栗山さん演出の『カリギュラ』や白井晃さんの作品とか、いろいろな舞台に出演されているので、連絡して相談に乗っていただきました。20歳ぐらいの時にKAATで『恐るべき子供たち』に語り部的な役で出演したのですが、演出の白井さんの言葉をかみ砕こうとしても煮詰まってしまって、助言をいただきたかったんです」
――松岡さんはどんな演劇体験を求めているのですか?
「演劇って、社会的な問題に立ち入ることが出来るのが強みだと思います。劇場という、非常に閉じられた空間の中で、そこにいる人たちだけで持つ共感覚というか、一緒にこの作品を考えるということが出来るのが魅力です。もっと僕らの生活圏に入ってきていいんじゃないですかね、演劇というものが。今、演劇はスター主義というか、この人が出ているから観に行くという傾向があって、それを否定はしないのですが、純粋に中身について興味を持ってくれたら嬉しいですよね。そういう方もチケットをとりやすくなって、いろいろな人が観にきてくれる世界になるといいなと思っています」
――松岡さんは今、ターニング・ポイントにいらっしゃるのかも?
「いえ、3年ぐらい前、20歳のころからこういう考えは持っています。19歳のころとは全く違います。これをやりたい、ということははっきりしています」
――松岡さんの演劇への思いが表れてくる今回の『スリル・ミー』、楽しみです。
「有難うございます!」
(取材・文・撮影=松島まり乃)
*無断転載を禁じます
*公演情報『スリル・ミー』4月1日~5月2日=東京芸術劇場シアターウエスト 公式HP
*松岡広大さんのポジティブ・フレーズ入りサイン色紙をプレゼントいたします。詳しくはこちらへ。